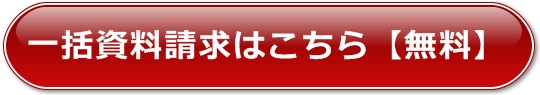社労士 社会保険労務士 用語集 な行、は行記事一覧
認可とは、法律上の行為に対して行政庁が介入することにより、法律上の効力を完成させる行為のことをいう。
人間関係管理とは、人間とは単に経済的動機に動かされるものではなく、集団に帰属して集団規範に従う連帯の存在であると見ることで、組織の共同目的を達成するためにコミュニケーションを図るなどして従業員を管理していくものをいう。
年功賃金とは、年齢や勤続年数に応じて昇給していく賃金制度。
年俸制とは、支払方法を問わず、労働者に支給する基本的な賃金の全額を労働者の一年間の業績に対する評価などにより決定し、一年分をまとめて提示する賃金制度をいう。
ビジネス・キャリア制度とは、ホワイトカラーの体系的・継続的な職業能力開発を支援するための制度をいう。
ビジネスゲームとは、経営者・管理者の管理能力の向上、意思決定能力の訓練など、広範囲の経営スキルの開発を狙った研修方法。経営のモデルを用いて、それに沿って経営成果を競い合う。
ビジネスコーチングとは、潜在能力を最大限に引き出すことを目的として従業員の意欲を刺激することで、人材を育成していく手法。
被保険者期間とは、厚生年金保険において、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの、月単位で計算される期間のこと。
年俸制とは、支払方法を問わず、労働者に支給する基本的な賃金の全額を労働者の一年間の業績に対する評価などにより決定し、一年分をまとめて提示する賃金制度をいう。
ヒューマン・アセスメントとは、職制上の上司ではない、特別に訓練されたアセッサーが、心理学を応用した一定の演習課題を通じて参加者の隠れた能力を観察評価し、その結果を人事施策や能力開発に活用すること。
病院と診療所とは、医療法において、20床以上の医療機関を病院、それ未満の医療機関を診療所と定めている。
非労働力人口とは、15歳以上の人口中の就業者および完全失業者以外の総数をいう。
ブレーンストーミングとは、創造性・アイデアの開発に広く使われる手法。グループをつくり、くつろいだ雰囲気の中でアイデアを出させ、後からそのアイデアを整理してまとめ上げる。
複線型雇用管理(コース別雇用管理)とは、複数の職掌を設定して、それぞれにおいて処遇を分けて雇用管理を行う制度をいう。