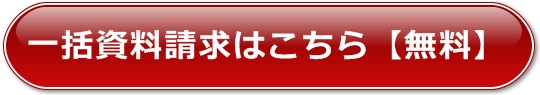社労士 社会保険労務士 用語集 た行記事一覧
怠業(サボタージュ)とは、「たいぎょう」と読む。労働者の団体が自己の主張貫徹のため、意識的に作業能率を抑制すること。
第二基本給方式とは、基本給を退職金の基礎となる部分とならない部分に分割し、退職金を算定する方式。
仲裁とは、当事者が仲裁結果に従うことを前提に手続きに入るもので、仲裁結果は当事者を拘束すること。
調停とは、調停案を当事者に受諾させることに重点を置いて解決を図ること。
短時間就労者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ40時間未満である者。
短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ30時間未満である者。
短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ30時間未満である者。
TWIとは、Training Within Industryの略。現場監督者用の訓練で、仕事の教え方・仕事の改善・人の扱い方の向上を目的にするもの。
TQCとは、製品の品質管理を製造部門だけに任せるのではなく、全部門が組織的に取り組む品質管理。総合的品質管理と訳される。
提案制度とは、従業員から作業方法や製品についての改善案を提案させて、その中から実施可能なものを採用することで、業務の改善を進めていく制度。
定期昇給とは、一定期間勤務し、一定の条件を満たした従業員に対し、あらかじめ定められた基準に従って毎年一定の時期に、個別に賃金を引き上げるもの。
定年制とは、就業規則等により定められている退職年齢に到達すると自動的に雇用関係が終了する制度。
適性検査とは、本人の適正がどのような面に向いているかを判断するために行われる検査のこと。
テレワークとは、情報通信機器を活用した在宅勤務のこと。
同盟罷業(ストライキ)とは、「どうめいひぎょう」と読む。労働者の団体が自己の主張貫徹のために、一時的に作業を停止すること。
特定水面には、陸奥湾、富山湾、若狭湾、東京湾、伊勢湾、大阪湾、有明海、および八代海、大村湾、鹿児島湾が指定されている。
独立行政法人とは、国が自ら提供してきた行政サービスのうち、一定の仕事をこれまでよりも柔軟に行えるようにして質の高いサービスを提供するために、国から独立させた組織。