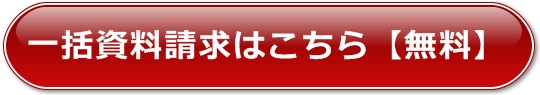社労士 社会保険労務士 用語集 さ行記事一覧
再雇用制度とは、定年年齢に到達した者を一旦退職させたあとに再雇用する制度。
作業所閉鎖(ロックアウト)とは、労働者の争議に対抗する手段として、使用者が事故の主張を貫徹するために行う、労務の提供を集団的に拒絶(作業を停止)したり、事業場から集団的に締め出したり、退去を求めるなどの行為がある。
JSTとは、Jinjiin Supervisor Trainingの略。事務部門の管理監督者を対象とした教育訓練であり、人事院が開発したことによりこう名づけられた。
自己啓発とは、労働者個人の自発的意思をもって自己の能力を開発使用とするもの。
自己申告制度とは、従業員各人の能力開発・人事異動などに関する希望を会社に申告させる制度。従業員の自己認識・自己啓発の機能を発揮させるというメリットがある。
仕事給とは、労働者の従事する職務やその遂行能力などの作業的要件に対応して決められる賃金。
CCSとは、Civil Communication Secitonの略。最高経営管理者層を対象とした訓練のことで、企業の方針や組織運営などの経営管理の全般について行う。
実質賃金とは、労働者が労働の対価として実際に受け取る名目賃金を、その時点の物価水準で除した賃金。実際の購買力を示すといわれる。
四半期とは、1〜3、4〜6、7〜9、10〜12月までの1年を3カ月ごとに区分した期間のこと。
社会保障協定とは、「年金通算協定」とも言う。日本以外の国で就労する場合(又はその逆)において、どちらの国でも年金に加入しなければならないという「二重加入」を回避するため、又は両国において年金制度に加入した期間を通算することができるなどの内容で締結された協定。(ただし協定内容はすべて同一ではない)
社内報とは、企業内でコミュニケーションを図るために作成される情報誌のこと。
社内人材公募制度とは、ある特定のプロジェクトや事業を行うための要員や欠員補充の募集源を社内の自由公募に求める制度。応募する場合、通常は本人の上司を経由しないで応募することができる。
昇格とは、資格制度において、その資格が上昇すること。
就業規則とは、使用者が定める、事業場における詳細な労働条件についての規則を指す。
就業者とは、労働力人口中の完全失業者以外の者(自営業者・家族従業者および雇用者)の合計を指す。
昇格基準線とは、新規学卒者が入職し、勤務につれて標準的に昇格昇給した場合、基本給がどのように変化するかを描いたもの。
承認とは、国又は地方公共団体が、他の機関または人の行為に与える同意のこと。
所轄公共職業安定所長とは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長のこと。
職種給とは、職種に対して決定される賃金。主に企業外の職種別賃金相場によって決定される。
職掌とは、「しょくしょう」と読む。職務分類において最も大きな分類となる区分。たとえば管理職・技術職・専門職などの区分を指す。
職能給とは、職務遂行能力を基準として決定される賃金。日本で発達した賃金類型のため日本で広く普及している。職能給導入には、職務遂行能力を分類するための職能分類制度と、個々の従業員の能力を判定するための人事考課制度が必要となります。
職能資格制度とは、職務遂行能力、技能、経験などにより従業員を処遇する制度のこと。
職場懇談会職場懇談会とは、職場内での意思疎通を図るため、意見交換を行う目的で行われる懇談会のこと。
職務とは、仕事を区分する概念のひとつで、職種と職位を要素として構成される。たとえば、営業職という職種にあり、課長という職位にある場合、営業課長が職務となる。
職務拡大とは、職務が単調化・定型化されることにより生ずる疎外感・単調感を防ぐために、細分化された職務を1人に担当させるのではなく、職務の構成要素となる課業の数を増やして仕事の範囲を拡大すること。
職務再設計とは、職務が負担にならないよう、かつモラールの維持、向上のために職務を再設計すること。
職務給とは、職務ごとに価値の高低を定め、その価値に応じて決定される賃金のことを指す。「同一労働同一賃金」の原則に立つもの。
職務評価とは、個々の職務について、職務分析に基づき、相対的価値を評価すること。職務給の導入や人事考課の基礎として主に用いられる。
職務評価とは、個々の職務について、職務分析に基づき、相対的価値を評価すること。職務給の導入や人事考課の基礎として主に用いられる。
職務明細書とは、昇格・昇進や採用基準などに利用するため、職務記述書から職務内容・職務に必要な資格要件などを抽出し、必要事項を明確に記述したもの。
紹介予定派遣とは、一定期間派遣形態で働いた後、派遣労働者とその派遣先企業が雇用契約を締結し、派遣先の社員として働くことができる仕組み。
昇進とは、役職に就くなど組織上の職位が上昇すること。
職位とは、職務の遂行に必要とされる権限と責任を伴った地位のことで、具体的には係長職・課長職・部長職などに区分される。
所定外給与とは、所定労働時間外の労働に対して支払われる賃金のこと。
所定外労働時間とは、所定労働時間を越えた労働時間のこと。
所定内労働時間とは、労働協約や就業規則において定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間。
ジョブ・シェアリングとは、勤務時間などを調整し、企業内における仕事を分かち合う制度のこと。
ジョブ・ローテーションとは、従業員が就く職務を1つに固定せず、いくつかの職務を定期的・計画的に経験させる制度。
新規求人倍率とは、公共職業安定所に、その月に新たに登録された新規求職者数に対する新規求人者数の割合。
人事異動とは、人事の活性化・欠員の補充・配置管理のミス修正のために行われるもの。縦の異動(垂直的異動)と横の移動(水平的異動)がある。
じん肺とは、ある種の粉じんを吸入することで、肺に線維性増殖性変化を起こす疾患。進行すると肺の機能である酸素の吸入が十分にできなくなる。潜伏期間が非常に長いことでも知られる。
進路選択制とは、中高年齢の者に対し、定年まで勤務・関連会社への出向・早期退職・専門職に就くなどの進路を複数提示し、そのいずれかを選択させる制度。
スキャンロン・プランとは、売上高に基づき賃金総額を決定する方式のこと。
成果主義賃金とは、会社の業績に対する貢献度や経営課題の解決に対する貢献度など、仕事の成果に応じて賃金を支払う制度のこと
セーフティネットとは、失業者の生活の安定を守り、次の就職を容易にするために設けられているもの。雇用保険制度などもその一つ。
センシビティ・トレーニングとは、態度変容を目的とした体験学習技法のひとつをさす。
早期退職優遇制度とは、一定の年齢以上の者が定年到達以前に退職する場合に、退職金などを優遇する制度。
総合決定給とは、仕事的要素、俗人的要素を総合的に勘案して決定される賃金を指す。
総実労働時間とは、労働者が実際に労働した時間を指す。
属人給とは、勤務年数・年齢・学歴などの労働者の諸条件(属人的要素)を元に決定される賃金のこと。
組織開発とは、組織に活力を与え、組織の体質を改善しようとする活動のこと。
組織のフラット化とは、階層数を少なくし、組織構造を簡素化すること。
損害賠償額の予定とは、債務不履行の場合に賠償すべき賠償額を、実害のいかんに関わらず一定の金額として定めること。
小集団活動とは、職場内において自主的に小集団を作り、自主的な運営によって問題点を改善しようとする活動のこと。
専門職制度とは、専門的な能力や知識を有する従業員をライン管理職とは別に配置し、ライン管理職と同等の処遇をする制度。