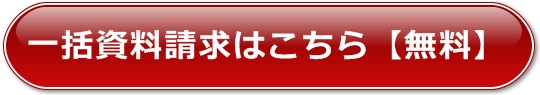社労士 社会保険労務士 用語集 か行記事一覧
カウンセリングとは、専門の知識・経験を持った相談員などにより、従業員の仕事上の悩みなどについて面接相談にのること。
科学的管理法(テーラーシステム)とは、アメリカのテーラーが提唱した管理法。工場における労務管理の手法として導入したものの作業標準を設定して、達成した労働者には高い賃率を適用し、達成しない労働者には低い賃率を適用して賃金を算定するという、差別的出来高給を採用したもの。
カフェテリアプランとは、福利厚生施設の提供を全従業員の一律なものとして行うのではなく、個々の従業員のニーズに合わせて複数のメニューよりそれぞれが選択して給付を受けることができるようにする制度。
「かんかつ」と読む。社労士試験の勉強中においては、被保険者・受給資格者などの住所又は居所を管轄する公共職業安定所長のことを主に指す。
完全失業者とは、就業が可能な者で各月の最後の1週間に収入を伴う仕事に1時間以上従事せず、かつ求職活動をした者を指す。
完全失業率とは、「かんぜんしつぎょうりつ」と読む。労働力人口に占める完全失業者の割合を指す。
キャリアディベロップメントプログラムとは、CDPともいう。長期的な視野で、労働者個々人の目標に沿って計画的な職務転換・配置転換を行い、職務経験を積み上げることにより人材育成を行うこと。
キャリア・パス(キャリア・パターン)とは、昇進を含めた配置移動のルートと異動の際の基準・条件のこと。
求人倍率とは、「きゅうじんばいりつ」と読む。求職者数に対する求人の割合。
QWLとは、Quality of Working Life。産業の発展によって人間性喪失・人間疎外の減少が顕在化したことに伴い、人間を仕事に合わせるというマネジメントの反省から、労働者の人間性を重視して、人間性の特性が活かせるように条件を整備し、最終的に生産性の工場を目指そうとするもの。
許可とは、(本来禁止されている)事項に対して、特定の条件の下にその禁止を解除すること。
勤務延長制度とは、定年の年齢に達した者を退職させずに引き続き雇用する制度。
苦情処理とは、職場で発生する不平不満を、団体交渉等によらずに日常的に解決するために設けられている制度。
経営参加とは、労働者が何らかの形で、企業の経営にその意思を反映させること。
ケーススタディとは、事例研究のこと。原理原則を知識として教え込むのではなく、まず教材として現実に起こった事例を用いて、さらにそれに基づくグループ討議を行うことにより、単なる知識ではなく知恵として身につけさせる訓練方法。
ケースメソッドとは、現実に起こった事例を教材として、グループでの討議を行い問題解決の能力を高めること。
現金給与総額とは、賃金・給与など名称に関係なく、使用者が労働者に支払った現金給与の総額。
行動科学とは、人間関係論では人間性の回復に重点を置き、人間の理論を強調するあまり経済的な能率を軽視した面があったため、フォーマル組織における能率の理論に意義を見出し、インフォーマル組織の利点に能率を加えるという、人間感情の理論と融合を図ったもの。
雇用者とは、会社・官公署・団体・自営業主または個人の家庭に雇われて賃金等を得ている者、および会社・団体の役員を指す。
雇用のミスマッチとは、労働市場において需要と供給の質的一致をみないこと。
雇用調整とは、不況期に発生する雇用過剰を調整すること。
コンピテンシーとは、高い成果を継続的に挙げるために必要な能力のこと。行動特性とも言う。賃金・人事制度において成果主義を採用する企業で、最近人材評価の手法として採用されることが多い。